|
遊園地
「ケロちゃんにあいたいのお」
目の前にいる三歳の男の子は大声でこの言葉を連呼していた。部屋の床がみしみしと音を立てているのは男の子が地団太を踏んでいるからだろう。
こういう時の子供は怪獣と同じだ。何をいっても聞く耳を持たない。悲鳴にも近いような、いきりたった声に私はほとほと困っていた。むっとした暑さがさらにストレスをためていく。
世間は夏休みを迎え、遊園地は人であふれ返っていた。
今日は遊園地自体に入場規制がかかっていた。着ぐるみショーも整理券がないと入れない。かえるを模したキャラクターは子供だけではなく、大人たちにも可愛いと評判だった。
もしかしたらこの男の子は遊園地に入場はしたものの、ショーは見られなかったのかもしれない。だからしきりに「あいたい」と言っているのだろう。
私はため息をついた。小さな子どもに大人の事情を喋るのはあまりいいものではない。せめてここにキャラクターのぬいぐるみがあったら男の子の機嫌も良くなっていたのかもしれないが、あいにくそういったものは置いていない。
自分の望みが叶わないと悟ったのか、男の子はとうとう泣き出してしまった。
「ケロちゃんにあうのー。あえなきゃヤなのーっ」
さて。どうやってわがまま王子をなだめようか。
考えながら私は重い腰を上げようとする。が、尻を半分浮かせたところでその動きは止まった。別の子供が男の子の前に立ちふさがったからだ。
男の子より六歳年上の少女は手に持っていた紙を床に置くと、何かを口ずさみながら鉛筆を走らせる。流れるようなメロディに男の子の泣き声が嘘みたいに止まる。
「できた」
歌の終わりとともに少女は色画用紙を男の子に見せた。べそをかいていた顔がぱっと明るくなる。
「ケロちゃん!」
少女のかいた、かえるのキャラクターは子供にしては上手いものだった。
更に少女は自分の鞄を開く。出てきたのは絵の具セットだ。
「じゃあ、これでケロちゃんに色をつけてあげようか」
「うん」
少女はチューブ絵の具を手に取るとパレットの上に白、黄色、赤、青、黒の順に絵の具をのせた。
「ケロちゃんの帽子の色はなーんだ?」
「きいろー」
「じゃあこれ」
そう言って少女は黄色の絵の具を筆になじませる。画用紙に黄色の線がすっと伸びた。あっという間に塗りつぶされる。
「おめめは何色かな?」
「しろとくろー」
「おくちは?」
「あかー」
男の子は少女の質問にどんどん答えていく。少女になついたのか、男の子は饒舌に語っていた。
「あのね、ケロちゃんのおなかのほしはきいろなの。でも、ぼうしについているほしはあかなんだよ」
少女は手を動かしながら相槌をうっている。鮮やかな色が次々と紙の上に乗せられていく。
すると男の子はあることに気がついた。
「おねえちゃん、みどりがないー。ケロちゃんのみどりがなーい」
確かにパレットの上にはキャラクターの特徴である緑色がない。
「みどりがないと、ケロちゃんにならないよ」
だが、少女はとても落ち着いていた。男の子に筆を持たせ、それを自分のてのひらに包みこむ。
「こうやって黄色と青をのっけてぐりぐりーってしたら……」
「あ」
男の子の目がきらきらと輝いた。
「ケロちゃんのいろになったー。すごーい」
紙の上で、緑色を含んだ筆がくるくると踊り始める。最後の色が加わると、敬礼をしている宇宙人のキャラクターが完成した。
小さな絵描きの気転は私の溜飲を下がらせた。これはよくある色の手法。だが、絵というものから遠のいていた私の頭の中には「色の原理」がすっかり抜け落ちていた。
いつの間に忘れてしまったのだろう。
気がつけばこの世界はたくさんの色で満ちている。でもそれらのほとんどが別の色どうしが重なり合った結果であることをどのくらいの人が覚えているだろう?
園内にある木々の葉も、涼しくなれば徐々に赤みを帯びていく。朽ちても冬を越えれば新しい芽が柔らかい緑をひきつれてやってくる。見上げた先には、空。今日は快晴で雲ひとつない。この高く澄んだ空間も今日だけは「青」というひとくくりで表現するのは勿体ない気がしてきた。
視線を子供たちに戻す。彼らは出来上がった絵を手のひらのうちわで乾かしていた。男の子は絵筆を持ったままだ。そばに転がっているのは五色の絵の具。
今の子供たちの瞳に、この空はどう映るのだろう――
そんなことをぼんやりと思っていた時だった。
「りょう!」
悲鳴にも近い声に、男の子の体が反応する。
「ママっ」
男の子は持っていた筆を投げ出すと迷わず母親のもとへ向かう。わが子を見つけた母親の目には少しだけ涙がにじんでいた。
「ばかっ。どこにいってたの。すっごく心配たんだからねっ」
一方、少女は戸惑いの表情を浮かべていた。嬉しそうな、それでいて少しさびしそうな顔。
私は少女の頭をそっとなでた。
ここからは本業である私の出番だ。
「『りょう』くんのお母さんでいらっしゃいますか?」
「はい」
「りょうくん、ショー会場にひとりでいたそうです。こちらのお嬢さんがりょうくんに気がついて、ここまで連れてきてくれたんですよ」
私が少女のことを紹介すると、母親は少女に深々と頭を下げた。
「りょうを見つけてくれてありがとう」
「そんな。こっちこそりょうくんに遊んでもらったというか……」
「ママみてー。ケロちゃんかいたのー」
「あら、上手にかけているじゃない」
母親は渡された画用紙を見て微笑んだ。本当はそのほとんどは少女が描いたものだが――まあ、いいか。
今度こそ母子の手はしっかりとつながれた。二人が描いた絵は乾いた所で筒状に丸められ、小さなリュックの中へおさまった。
「おねえちゃん、ばいばい」
「ばいばい」
母子の姿が人ごみの中へ消えていく。男の子――りょうくんは何度も振り返って手を振っていた。同じように手を大きく振り返す少女の顔からは満面の笑みがこぼれていた。
平日とはいえまだ夏休み。この遊園地は人であふれている。時計は三時をまわっていた、だが、この場所から見た限りでは家に帰るような気配すらない。きっとこの世界にまだ浸っていたいのだろう。どきつい原色に埋められたこの場所も彼らにとっては夢というフィルターがかかった優しい空間なのかもしれない。
うーんと背伸びたあとで、私は大きく深呼吸した。
それにしても、と思う。
「『みちるちゃん』のお母さんはなかなか見つかりませんねえ」
「……ですね」
「もう一度園内放送かけましょうか?」
問いかけると、頬を赤く染めた少女――みちるちゃんはこくりと頷いた。(了)
(参考)
ケロロ軍曹
(あとがき)
こちらは「読み物.net シアン大賞」への投稿作品です。
最初は特撮もののヒーローを描く話だったのですが、レッド以外のヒーローを好きな子供っているのかなぁ、と思い、かの宇宙人へと変更しました。
つたない物語にも関わらず下読みをしてくださった さくらみかん さんに感謝します。

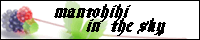
|